2010年01月05日
謹賀「森」年


遅ればせながら、あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
年末は忙しくて、とてもブログどころでは無かったのですが、「森とま材の家」の材料出しをしていました。
これから報告していければと思います。
今年はSGEC も含めて、より身近な地産地消を進めます。
GWには木工展にも参加する予定です。
今年の Myテーマは「安倍奥、安倍町」です。
2009年07月02日
アンドロイドは電気羊の夢を見るか?


ニセモノ、模造品(=レプリカ)
最近、木材関係の人たちとの何気ない会話の中に、
「本物がどんなものか、多くの人が知らない。」
というフレーズを多く聞きます。
今更の議論かもしれませんが…。
建築基準法という法律が
「日本人をビニールハウスの住人にした。」
野菜ならビニールハウスもいいけれど…、人間はちょっと…。
プリントの木目を本物と思っている人…。ツルツルに輝く塗装をかけられた床材に、もはや木の温もりある手触りはありません。
人工乾燥(高温乾燥)された杉材が出回り、若い大工さんも
「本来の杉の色と香り」
を知らないという現実がもうそこまで来ています。
「10年もすれば墨付け出来る大工さん、手刻み出来る大工さんが居なくなる。」
とささやかれて久しいですが、
「杉って、焦げ臭くて、黒っぽい木でしょ?」
こんな会話が聞かれるのもそう遠い未来では無いかもしれません。
本物より、レプリカの方が性能が良かったりする昨今ですが、
「木に代わる素材を人間は造り出せない。」
人は木と何億年もかけて友達になってきたのですから。
…でも映画「ブレードランナー」では、主役のハリソン・フォードよりも、レプリカの人間(レプリカント)のルトガー・ハウアーの方がカッコいいと思ったりするのです(笑)。
2009年06月16日
つぐみぐみ


いつも携帯のカメラで気軽に写真を撮っていたのですが、
毎日、仕事をしながらポケットに入れて持ち歩いていたせいか、
カメラレンズの前のプラスチックがキズだらけになって、ピントさえ合わない状態となりました。
こうなると、思う時に写真が撮れず、良いチャンスを逃す事も。
マイペースなブログですが、それでさえカメラ無しでは不安で不安で…。
世の中便利すぎて、本来無くても済むものさえ、無いと不安になる、妙な時勢です。
グミ。毎年よく実ります。木によって良く実る木と、実りの悪い木があるそうで、
昔からあるこの木は当たりの木みたいです。
よく実るから挿し木してみたいと、枝を欲しがる人も。
渋いので沢山は食べれませんが、ヒヨドリが大挙して押し寄せ、1日で無くなってしまうのが毎年の通例です。
2009年05月22日
プロの道具


プロが愛用している道具というのは、作りもデザインもしっかりしていて、ついつい欲しくなってしまいます。
こちらは、宝石商をしている友人から、無理言ってゆずっていただいたルーペです。拡大鏡は金属のフレームに収まっていて、使う時は横にスライドさせます。使う時以外はガラス面を保護しています。
そして、専用の皮のケース。これも本体にジャストフィット。
小さなものですが、大きさの割に重量があり、信頼感があります。
で、これを主に何に使っているかと言うと…。
木のトゲを抜く時に愛用しています。拡大してトゲの深さや方向を見て、針でチクチクやります。
仕事柄、トゲ抜きはしょっちゅうやってます。放っておくといつまでも痛いんです。
本当に小さな小さなトゲなんですが…。
でも、これを使うたびに、最近は会わなくなってしまった、宝石商の友人を思い浮かべます。
2009年05月21日
子供のピアノ

 先日、子供のピアノ発表会がありました。生徒さん全員60名ほどの教室なので、次々と数分程度の楽曲を披露していきます。
先日、子供のピアノ発表会がありました。生徒さん全員60名ほどの教室なので、次々と数分程度の楽曲を披露していきます。子供は熱心にピアノをやっている風でも無いのですが、「やめる?」と聞くと「続けたい」という返事が返ってきます。
押し付けてやらせている訳では無いのですが、私のわがままで幼稚園の頃からピアノ教室に通わせ始めました。
私もちょっとバンドなどやっていた時期があったのですが、絶対音感はおろか、移動音感も無いような状態で、努力だけでは容易に克服できないものが音楽には付いてまわります。小さい頃得たもの、感じたものが素養となって、その大切さに大人になってから気づきます。
自分に音感が無い事に気づいた時、しばらくは劣等感でいっぱいでした。
「自分の子供には、どんな道に進んでもいいような素養をつけさせたい」と、その時から思うようになりました。
別に音楽家にしようとは思ってもいませんし、音感の有る無しは将来性にさほど影響はないでしょう。
でも、塾に通わせるより、今は音楽に触れて欲しいと願っています。いつかその大切さに大人になって気づいてくれるはずだと…。
親の勝手がついつい出てしまう、子育ての難しさ(楽しさ)でしょうか。
…さて次は、音楽教室では教えてくれない「リズム感=ビート&グルーブ」をどう体得させるか。
親バカは尽きません(笑)。
2009年05月10日
母の日の薔薇たば


数年前までは、母の日には植物の鉢植えを(半分自分の趣味で)贈っていたのですが、どんどん鉢植えばかりが増えてしまうので、ここ数年は自宅まわりに咲くツルバラを切り花にして渡します。
しかしツルバラは花までの茎の長さが短かったり、長い枝に沢山のつぼみが集団でついていたりと、とても切り花にしにくい…。
おまけに下向きに咲く花も多いので、花瓶に上手に収まらないのです。
で、写真のような笑っちゃうような形にいつもなってしまいます。
こういうアバウトの状態でも、気持ちだけ伝わればま、いっか〜ということで…。
グラハム・トーマス(黄)
ウイリアム・モリス(ピンク)
ピエール・ド・ロンサール(赤白)
シラン(友情出演)
脚立を立てて、花の中に顔を入れた時の、甘い香り。。
でも、ふと気づくと、顔や腕がバラの刺でヒリヒリです…。
2009年05月04日
「めぐる」と「はんこ」


石井かほり監督の映画「めぐる」。
木版染めといって、木を削ったハンコを布地に押して反物の模様を作る職人の物語です。
静かな空間で繰り返される丹念な作業。気の遠くなるような行程の繰り返しで、美しい模様が生み出されていきます。

このDVDを見ていたら、隣で子供も一緒に見始めました。子供には退屈かもしれない映像物語なので、すぐに飽きた様子だったのですが…。
どうも、木版を掘る映像にピンときたらしく、消しゴムハンコを持ち出して、気がついたら映画と同じ桜の花模様のハンコを作っているではないですかぁ!
ちょっとした花びらのアクセントなどもちゃんと入っていたりして。
短い時間によく観察して見ているものだと感心してしまいました。
消しゴムハンコを買ってあげても、何を掘って良いのか解らなくて、そのまま使われずにいましたが、ちょっとしたきっかけで、あっという間に幾つも彫り上げてしまいました。
秘密兵器「デザインカッター」を貸してあげたら、さらに上達したようです。
ちょっとヒントをあげると、子供は想像を広げていってくれます。
自主性を大切に育てていきたいものです。
2009年04月08日
酒肴旬菜 萌木さん。


以前上棟の時に紹介させていただきました、和風店舗のお店がオープンしました。
構造材から内装まで、随所に地域の杉と桧材を使用していただき、とても落ち着いた雰囲気に仕上がっています。



開店のお祝いに、関わった業者さんを呼んで食事会まで企画していただき、とても美味しい料理をごちそうになりました。
大工の棟梁さんが、こつこつと仕上げた内装から、小物類まで、木の雰囲気が優しいお店です。
今度家族と一緒に食事に行こうと思っております。
 2階は自宅となっていますが、床材にも杉のフローリングを使っていただきました。素足でも冷たさを感じない杉材の床。キズは付きやすいかもしれませんが、立っていても疲れを感じない、優しい床板です。
2階は自宅となっていますが、床材にも杉のフローリングを使っていただきました。素足でも冷たさを感じない杉材の床。キズは付きやすいかもしれませんが、立っていても疲れを感じない、優しい床板です。お手頃価格のランチもありますので、ぜひ寄ってみてください。
酒肴旬菜 萌木(もえぎ)
静岡市駿河区池田197-1
tel. 054-263-3321 [休]月曜 [P]8台
[営業時間] 11:30〜14:00 , 17:00〜22:00(日曜はランチのみ営業)
ランチ全8品 ¥680
大きな地図で見る
2009年02月28日
ホワイトウッドは怖いどウッド


「ホワイトウッドは怖いどウッド」というタイトルでコラムを自分のHPで書いてから3年。いつの間にか「ホワイトウッド」で検索をかけると最上段にヒットするページとなり、トップページよりもアクセス数の多いページになってしまいました。
別に狙った訳でもなく、なんだか皮肉な出来事だなあ、と感じております。
ページそのものはホワイトウッドについてのネガティブキャンペーンですし、私個人としても不本意なページです。
でも、工場にホワイトウッドの件で問い合わせがよく来るようになりました。
「もっと詳しく聞きたい」---- 工務店が木材について曖昧な樹種を言っている。
「お施主さんが国産材で家を造りたいと言っている。」--- 建築事務所。
大まかに言うとこの2種類の問合せです。出来る限りの説明をしていますが、自分の仕事には結びつきません(笑)。
しかし、少なくとも2例、ホワイトウッドの使用を止めて、国産材に変更したのではないかという感触がありました。
潜在的にはもう少し、このページを見て考えを変えてくれた人がいるのではないかと感じています。
「ネットの力」とでも言いましょうか、HPの記事で何らかの、人の考えや動きを変えられることもあるわけです。
このページで国産材振興の一端を担えたと、嬉しい反面、、
こんなページを書かなくて済むような建築業界にならないかと、感じ入る今日この頃です。
悪いのはホワイトウッドではなく、人間の考え方なのです。
※ 写真は 木材・住宅情報交流組織LICC(リック)による木材耐久実験です。右端の朽ちて崩壊しているがホワイトウッドです。
2009年02月09日
大工さんの風車


以前紹介しました、「世界の子供がSOS」というTV番組で、フィリピンの子供たちのために風車を作りに行った大工さん。
仕事場の脇に風車を作ったということで、見に行ってきました。

あいにく大工さんには会えませんでしたので、詳しい話は聞けませんでしたが、ポンプを繋げて、水が汲み上げられるような仕組みになっていました。
脇には、破損した羽があったりして、木製の風車ですから、ちょっとした強風で壊れてしまうこともあるのかと思いました。
風もなく穏やかな日でしたので、風車は回っていませんでしが、のどかな田舎といった昔の情景が見えるようです。
今度は風車が回っているところを見てみたいです。
2008年12月29日
ウッドなMac


もう随分前になりますが、Macの筐体を木製に作り替えてみました。
パソコンは高価ですから、壊しては損です。中古のものを取り寄せて、バラして筐体を木製に作り替えました。
ブラウン管の画面の曲面にそって木を削ったり、コードの差し込み口に細かく穴を開けたり。
当時はフロッピー起動でしたから、フロッピーの挿入口を細く作ったり。
木工作の習作としては複雑なものでした。

壊してしまう危険をおかして木製に改造したMac Classic 。作った当時はちゃんと起動して画面も映ったのですが、今は埃に埋もれてしまっています。隣にあるのは木製のマウスです。
木を削ったり、塗装したりといった作業がとても楽しかった、古い記憶のなごりです。
2008年12月16日
初めてのスケジュール帳

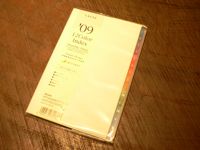
実は私は今までスケジュール帳という物を持った事がありません。
理由1:頻繁に人に会うほど忙しくない。
理由2:だから少々の日程や時間なら記憶しておける。
理由3:メモしたらその瞬間に頭から消える。出来るだけ記憶する事を心がける。
という事で今まで大きな失敗も無くやって来たのですが、しかし。。。
このところ物忘れが増えて来た
 のです。
のです。会合の日にちを1日間違えてしまってから、「ヤバい感じ」がしています。
歳のせいでしょうか・・・。(そうです。)
とりあえず文具店に行ってみましたが、山のようにあるスケジュール帳からどれを選んでよいやら、全く解りません。まあ、一番小さいもので足りるだろうという事で、ちょっと可愛いこんなのを選んでみました。月別のインデックスになっていて、すぐにその月に飛べます。はたして役に立つのでしょうか?
記憶があてにならない以上、これからはこまめにメモする事にします。
この歳でスケジュール帳デビューです。
2008年11月08日
「ひばり」の由来


「木の店ひばり」は「何で『ひばり』なの?」と時々訊かれます。
遡ること◯◯年前、ちょっとした病気をしました。胸にカテーテルを入れてベットから動けない状態で病室に居ました。
町中の小さな私立病院で、窓の外は電線と空が見えるだけで、退屈な毎日。
毎朝、スズメの大群が電線に並んで止まっていたのですが・・・
ん? あるとき、気づきました。ヒュンヒュンという鳴き声、翼の隙間からチラっと見える黄色い羽。
スズメではない、何て鳥だろう?
昆虫や動物は興味があってそれなりに知ってもいたのですが、鳥の世界は全く無頓着。スズメとツバメとカラスとトンビくらいしか知りませんでした。
退院してから、さっそく鳥類図鑑を買い込んでその鳥を探してみました。
「カワラヒワ」
これが鳥の世界へ興味を持った第一歩でした。
リハビリを兼ねて、双眼鏡と図鑑を持って、自転車であちこち鳥見をして歩きました。駿府城のお堀にカワセミを見つけた時の感動は今でも忘れません(今もいるのでしょうか?)。
それから鳥の世界へドップリという訳でもなかったのですが、身の回りにいる鳥なら分かるようになりました。
それからまた◯◯年たちまして、今のようにインターネットというものが発達する前には、「パソコン通信」というものがありまして、文字だけの世界で会話していました。そのパソコン通信で会話をするのに、「ハンドルネーム」今で言うニックネームで会話するのが一般的で、さあ、私も何てハンドルにしよう?と考えてみて。
元気な鳥のイメージの名前がいいなあ、と思って「ひばり」と付けました。美空ひばりさんとは関係がありませんが、イメージは近いと思います。それと、「ひばり」を逆さから読むと「りばひ」ですが、これが「リバティ」と発音できるので、ますます気に入ってしまったのでした。
「木」の世界に入り込んだのはその後で、「ひばり」の方が先なんです。
何て事ないネーミングですが、こんな由来で店の名前にまでなってしまいました。ロゴデザインも私が創りました。
ちなみに「つぐみ」は何となく可愛いイメージの単語なので鳥繋がりで付いた名前です。
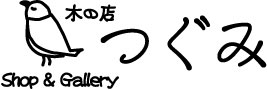
つぐみのロゴは、家内のいたずら描きが採用になってしまいました。(私がデザインしたロゴは却下されました。。)
2008年10月16日
栗むきムキに。

 沢山の栗ですが、甘栗のようにツルんとは剥けないので、半分に切って、スプーンですくって食べます。
沢山の栗ですが、甘栗のようにツルんとは剥けないので、半分に切って、スプーンですくって食べます。切って、スプーンでほじって、の繰り返し。
うゎあ〜、面倒だあぁ。
今度は剥く事に専念して、ムキになって1時間かけて容器いっぱいに栗を剥きました。
意外と重労働です。指がつってしまいました。
飛び散った栗のかけら。掃除も一苦労です。
この細かい粉の栗。どう食べるのが一番美味しいでしょうか?
栗きんとん。ごはんにかけて栗ごはん。モンブラン(これは無理)。
家族で考えてみましたが、どうもそのまま食べるのが一番美味しいようです。
タグ :栗
2008年10月14日
栗っく


某所へ栗拾いに行ってきました。すでに大量のイガグリが落ちていて、もう採り尽くされたか?と思いましたが、拾い残しもあるし、風に吹かれると、上からポトっと落ちてきたり。
子供と一緒に木の棒でつついて落としたり。
まだ木の上には沢山イガが付いていますが、とても届きません。
来週あたりには、落ちてくるかな?
今日、茹でて食べました。甘くて美味しい、秋の風味です。
タグ :栗
2008年10月07日
40年使った研石

 お世話になっている大工棟梁の元へ、はるばる埼玉県から若い大工さんが修行!にいらっしゃいました。
お世話になっている大工棟梁の元へ、はるばる埼玉県から若い大工さんが修行!にいらっしゃいました。実は、私がこの棟梁の家づくりについて書いた記事が縁で、「棟梁に会って話を聞きたい」とやってきた、勉強熱心な方です。
今回で2回目の来訪。棟梁からノミの研ぎを教わっていました。
この棟梁が使っている砥石、何と40年使っていて、こんなに薄く!でも
「まだ20年は使える。」
と、棟梁。今の時代、良い研石はなかなか無いそうです。

若くてやる気のある大工さんも、ちゃんとした修行をする場が無いのでしょうか。
「また来ます!」
と車で埼玉まで帰っていきました。
ぜひとも棟梁のもつ伝統技術を受け継いで、次世代に繋げていただきたいと思います。
ガンバレ!
2008年08月29日
自分の仕事の価値

10月に出る「森とま通信」の秋号に載せる記事を書きました。
記事を書きながら、そもそも、製材所の存在価値って何なんのか、疑問に感じました。
写真や絵画や家具のように形に残る仕事ではない。
人の心に残る仕事でもない。
木を割ったり挽いたり(引いたり)、小さくマイナスにする作業。
マイナスをプラスに変えていく方法は探っても簡単には見つからない。


山から出て来たナラの木です。まともに製材してもモノになりそうにないので、あちこちひっくり返して製材して椅子にしました。
これも、仕事というより趣味の世界の作業だと思うと、本当に木を活かしてあげられたのかどうか、これでよかったのかどうか、妙な形の製材をすると感じます。小さく割って積み木にでもした方がよかったのかも。
小さくするのはいつでも出来るので、とりあえずこの木はこれで良しとしますが、屋外に置くとナラの木は容易に朽ちてしまうので、いずれまた手をかける必要が出来ます。
2008年06月02日
前向きな決断。


前回の内容はどうも負のエネルギーで、イカンなあ、と反省してます。
どうも内容が固いと感じる自分のブログ。よし、ならば、プラスのエネルギーでちょっと書いてみよう。
 。こんなぐあいに
。こんなぐあいに 顔マーク使ったりして
顔マーク使ったりして おっ、なかなか楽しいかも
おっ、なかなか楽しいかも

・・・これでいいのだろうか
 ?
?工場で棧積み乾燥させている板にバラが寄り添っていい感じに
 なりました。工場なのかガーデンなのかよくわからないのが私の仕事場です
なりました。工場なのかガーデンなのかよくわからないのが私の仕事場です 。イングリッシュローズのアブラハムダービー。
。イングリッシュローズのアブラハムダービー。後ろでは妻が・・こんなブログ書いてるなら森とまの会報誌仕上げたら?・・・といったきつい視線が
 。
。はいはい、これからちゃんとやります。

2008年06月01日
残念な決断。


工場の前の河原は、GWから夏にかけて、土日祭日の天気の良い日は、バーベキューの人たちで大にぎわいになります。
何か燃やすものを探しに製材所に来られても困るので、マキを無人販売していました。
警察からも「端材などを外に置かないようにお願いします」と言われていました。
一束¥100での無人販売。中にはコイン入れが解らず、工場まで代金を持って来てくれる方もいました。逆に、¥10しか入っていなかったり、置いたマキよりも金額が少ない事もありました。無人だから多少の持ち去りは仕方ないけど・・・。
でも、今回はゴッソリ持っていかれてしまいました。さすがにメゲました。
「ドロボウのために労力使う事は無い」
「ここにマキがある事を知って来る人もいるかもしれないから置くべきだ」
など、意見もありましたが、結果、中止に。
一部の人の心ない行為で、その他の人の利便が犠牲になる。
よくある事例です。。
2008年05月31日
地域産業体験受け入れて


中学校の生徒さんが、製材所へ2日間、地域産業体験ということで仕事のお手伝いをしていきました。中学校1年生(って3ヶ月前までは小学生ってこと)の女の子に、3K(きついきけんきたない)製材所で出来る仕事って・・・?
ということで最初はお断りしたのですが、本人がモノづくりが好きで・・とのことで「じゃあなんか作ってみましょう」ということで受け入れてみました。
広葉樹の皮むき、木材のラベル貼りなどして、ちょうど注文になっていたプランターをバーナーで焼く作業を体験していただきました。

こんなふうに焼き杉のプランターが出来ました。お疲れさま。大変だったかな?
今日、本人からお礼の手紙をいただきました。ちょっと感動! 受け入れるのは大変ですが、木のことやモノづくりの体験を通して何か将来のヒントになってくれればと思いました。



